更新日:2025.10.3
抗菌や抗ウイルス製品は身近な存在となっていますが、その評価試験や認証制度の仕組みはあまり知られていません。本稿では、抗菌製品の歴史やJIS規格に基づく試験方法、各業界団体の認証マークについて紹介し、空調分野での活用や衛生意識向上への期待を解説します。
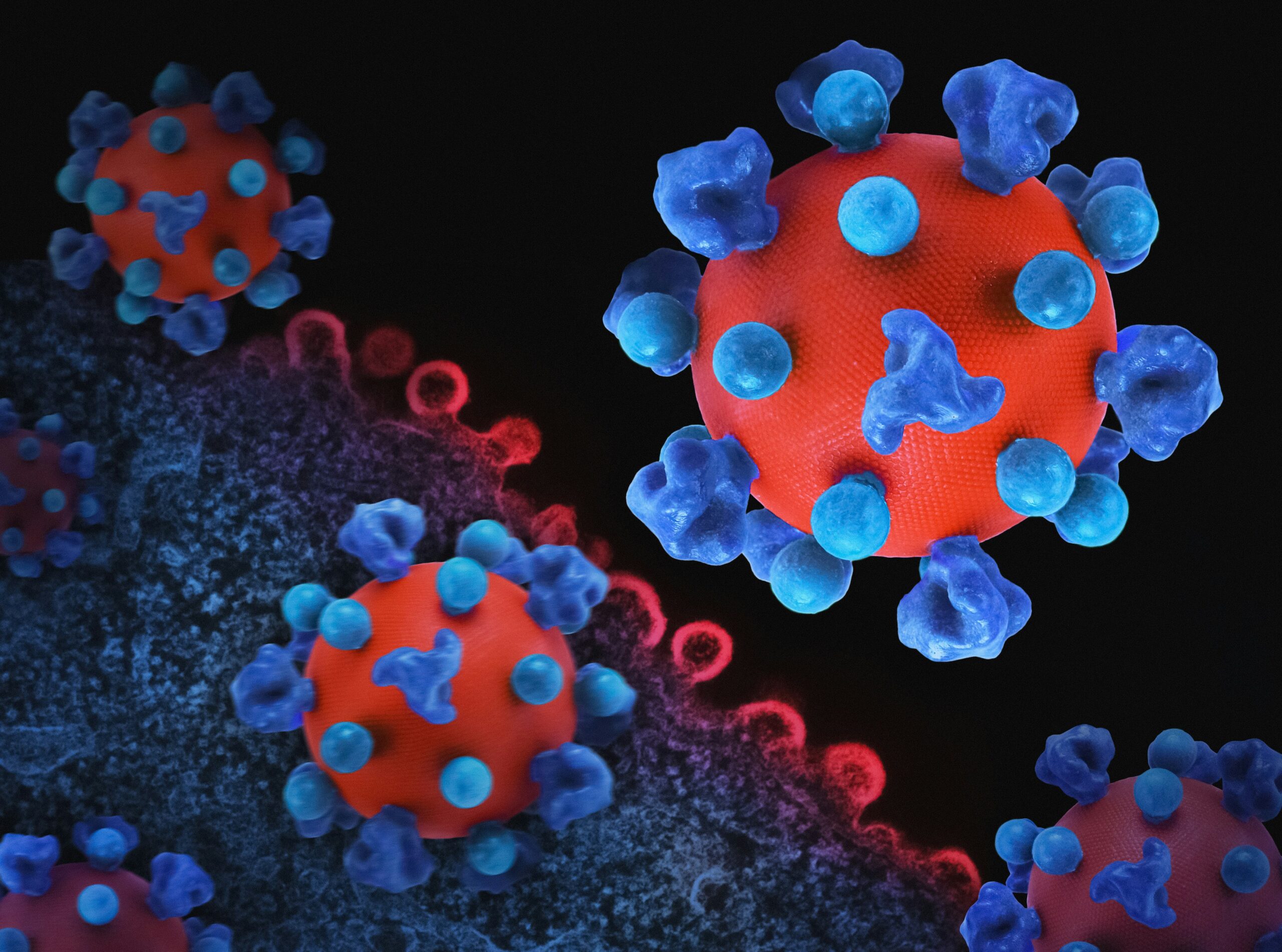
JADCA会員の皆様、昨年よりJADCAの微生物汚染対策委員会メンバーに参画しております菊野と申します。北里環境科学センターで、環境微生物調査や殺菌・抗菌試験、空気清浄機の浮遊ウイルス除去性能評価など、微生物関連業務に長年従事後、現在は参与として、また本年6月からは学会の会長となり、健康で快適な環境づくりを目標として活動しています。どうぞ宜しくお願いいたします。
「抗菌」や「除菌」は、社会に浸透し、今ではだれもが知っている言葉です。私は長年にわたり抗菌製品や除菌製品の評価試験を実施し、また規格作成にも関わりましたが、これらの言葉の意味を正しく伝える機会がないことを残念に思っていましたので、抗菌・抗ウイルスについて、少しだけ紹介させていただくことにしました。
殺菌、消毒の用語は、薬機法によって、医薬品と医薬部外品以外で使用することができません。そこで、薬機法の対象とならない細菌やウイルスに効果がある雑品にたいして、抗菌や抗ウイルスの表現が用いています。抗菌加工製品の販売は、1970年代に始まり、各社が独自の評価試験によって抗菌性を示していましたが、1990年代前半までの社会的な認知度は低いものでした。1996年に発生した腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒を契機に多くの抗菌製品が市場に溢れ、消費者の混乱を招いたことを契機として、安全面も含めたルールが求められ、1999年に通産省によって「抗菌製品ガイドライン」が策定されました。これをもとに、関係業界団体において評価方法もが標準化されました。今では、多くのJIS規格として抗菌・抗ウイルス性能の試験方法と評価基準が制定されています。それぞれの評価基準を満たせば、業界団体の認証マークを製品に表示が可能です。
抗菌製品の試験方法の例としてJIS Z 2801の試験概要を示します。試験菌には大腸菌と黄色ブドウ球菌を用います。対照(試験菌数を減らさない)試験片と抗菌製品から作製した試験片を用意し、その表面に試験菌液を滴下、所定条件で作用後の菌数を比較します。対照に比べて抗菌製品の菌数が1/100以下であることを抗菌性ありと評価する規格になっています。
抗菌・抗ウイルス性能に認証マークを定めている団体には、抗菌製品技術協議会(SIAAマーク)、繊維評価技術協議会(SEKマーク)、光触媒工業会(PIAJマーク)があります。



また、特殊な例としては、日本銅センターのCUSTARマークがあります。前述したJIS Z 2801規格の手順で試験を行った結果、試験品の菌数が対照の1/100,000以下になることを超抗菌の基準として超抗菌材料、超抗菌銅製品として認証するものです。

これらの評価試験の結果は、特定の試験菌や試験ウイルスに対する性能であり、実環境に存在する多様な細菌やウイルスに対して同じ性能を保証するものではありませんが、間接的に消費者に衛生意識を持たせる効果が期待できます。空調関連で活用されている代表的な抗菌剤には、ドレンパンのスライム、カビや菌の発生を抑制する抗菌剤があります。JADCAが担っている空調ダクトの清掃とあわせて、これらの抗菌製品が有効に活用されることを願っています。
一般財団法人 北里環境科学センター 参与
日本防菌防黴学会 会長 菊野理津子